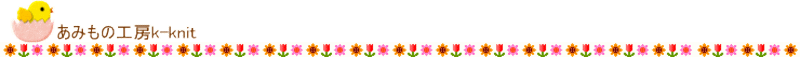
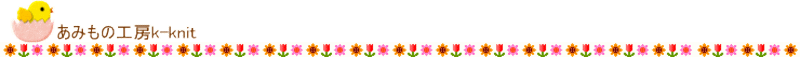
![]() ゲージってなあに?
ゲージってなあに?
| 「編物の本の通りに同じ糸、同じ編み針を使ってセーターを編んだのに、サイズが違ってしまった!」 な〜んて経験をお持ちの方はいらっしゃいませんか? その原因のひとつに、編む人それぞれの手加減が違うからという事があげられます。 せっかく編んだのにそれではがっかりです。 そんな事のないように作品を編む前には必ず、“ゲージ”をとりましょう♪ ゲージというのはいろいろな本に定義してありますが、簡単にいうと、10cm四方の編地の中に編目が何目、何段あるか、ということです。 たとえば、あなたのゲージが「20目×20段」だったとします。 作りたい作品が40㎝四方なら、作り目を80目して、80段編むという事です。 ゲージをはかる編地のことを「試し編み(スワッチ)」といいます。 この編地はこれから作る作品の基本となるものです。 ●試し編みをしましょう。 まず、編もうとする作品の編み糸と針で、15cm〜20㎝になるように作り目をし、作品の編地で正方形になるように編みます。 正方形に編みあがったら、編地を平らなところに置いてスチームアイロンをあてて編み目をととのえ、しばらく落ち着かせます。 編み糸によってはアイロンの温度が低かったり、かけてはいけないものもありますので、ラベルなどをよく見て確認してから行ってくださいね。 ●ゲージを測ってみましょう。 編み目がととのったら、編地の中央の一番編み目のそろっている部分に縦、横に定規をあてて、10cmの中に横が何目、縦が何段あるかを 数えましょう。 何か所か数えてみて、平均した目数、段数をだすと、より正確なゲージをもとめることができます。 以上は基本的なゲージのとり方ですが、ところがどっこい編地には編み目のわかりにくいものがあります。 そういった編地の場合は、別の方法でとりますがそれは別のページでお話しますね。 棒針編みの複雑なアラン模様や穴あき模様、かぎ針編みの模様編みなどがそうです。 編み目がわかりにくいだけなら模様編みの周囲に2センチぐらいずつ、メリヤス編みで囲むように試し編みをすると数えやすくなります。 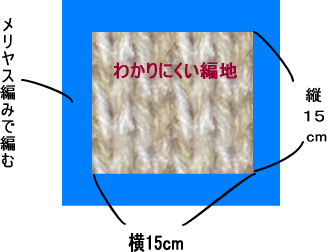 「な〜んか、めんどくさいなぁ…」と、思っているあなた!…イエ、実は私もですが…(^_^;) “試し編み”、“編み方の練習”と思ってがんばりましょう! 作品を編む前には必ずゲージをとる!それが満足できる作品を作る第一歩です♪ ちなみに私はあみぐるみを作るのに“ゲージ”はとりません。(とってる人っているのかなぁ…) あみぐるみはいきあたりばったりで編んでます。(後々のためにメモはとりますが…) “ゲージ”をとるのはあくまでも「身に付けるもの」だけでよいかと、私は思いますが…どうでしょう? |